朝ごはんの準備に、自分の支度に、子どもの声かけ…。 ママの朝って、ほんとうにバタバタしがちですよね。 そんな中で、子どもがいつまでも起きてこないと「早く起きなさい!」ってつい言っちゃう。 …でも、毎日それを繰り返すのって、しんどいですよね…。 今回は、 小学生の子どもが“すっきり朝を迎えられる”ようになるための、 夜にできる7つの習慣をまとめました🌙 ぜんぶやろうとしなくても大丈夫◎ できるところから、ちょっとずつ試してみてくださいね♪
なぜ朝起きられないの?子どもが起きにくい理由

「早く寝たのに、なんで起きられないんだろう?」
そう思ったこと、ありませんか?
朝なかなか起きられないのは、
子どもの「やる気」や「性格」だけが原因ではありません。
いくつかの要因が重なって、“起きにくさ”につながっていることが多いんです。
● 睡眠不足・就寝時間が遅い
● 寝る直前まで脳が活性化している
● 起きる目的がない(モチベが低い)
● 体内リズムが整っていない
● 成長や体質によるもの
朝起きるのって、大人だってしんどいときありますよね。
すっきり目覚めるのは子どものためにもなるんです◎
このあとは、朝の目覚めをラクにする“おすすめの夜の過ごし方”をお伝えします。
朝すっきり起きるために!夜やっておきたい習慣7選
① 21時台には布団へ!しっかり身体を休める時間を◎
小学生の理想的な睡眠時間は、6~13歳で“9~11時間”といわれています。
(出典:米国国立睡眠財団)
たとえば朝6時に起きるなら、できれば21時には布団に入るのが◎
睡眠時間が不足すると、ただ朝がつらくなるだけじゃなく…
- 学校で集中力が続かない
- 日中に眠くなる
- イライラしてしまう
など、いろんな影響が出てしまいます。
💬 筆者のひとこと 私自身、子どものころはなかなか寝付けず、 布団の中でただゴロゴロしている時間が長かったタイプです。 そのとき母が言っていたのが、 「眠れなくても、横になって目を閉じるだけでも身体は休まるからね」。 今は娘にも同じように伝えていて、 “眠れなくてもまず暗くして、布団に入ってみる”を心がけています。
② 寝る前のルーティーンを決める

夜、布団に入る前や入るときに“お決まりの流れ”を作るのもおすすめです🌙
未就学児のころは、
絵本を読んだり、1日の出来事をおしゃべりしたりと、
“寝かしつけ”の時間が自然とありましたよね。
小学生になった今は少し大人になった気持ちで、
自分だけのルーティーンを取り入れてみるのも◎
- ストレッチをする
- 好きな本を読む
- やさしい音楽を流す
- ひとこと日記を書く など…
毎晩決まった流れができると、自然と眠りに入るスイッチにもなります✨
③ 次の日の楽しみを用意しておく

「まだ起きてたい!」「寝るのもったいない!」
そう思うのは、子どもなりに“やりたいこと”があるからなのかも。
そんなときは、
「その楽しみ、明日の朝にとっておこう!」と声をかけてみてください。
- 漫画の続きが気になる
- 絵を描きたい
- ゲームの続きをやりたい など…
「それなら、朝ちょっと早く起きてからやってみよう♪」と提案すると、
自然と自分から目覚ましをかけて、起きようとする子も多いです◎
④ 朝の“流れ”を一緒に確認しておく
「朝起きてから何をするか」をあらかじめ決めておくと、朝のスタートがスムーズになります。
起きた直後はまだぼーっとしていても、
やることが明確になっているだけで、自然と動き出しやすくなります。
「◯時に起きて、顔を洗って、朝ごはん食べたら…」と
一緒に確認しておくだけでも、子どもにとっては安心感に◎
“ちゃんと朝起きなきゃ”という意識づけにもつながりますよ♪
⑤ お風呂は寝る1時間前までに入っておこう

寝る直前にお風呂に入ると、身体が温まりすぎてしまい、かえって眠りにくくなることがあります。
できれば、就寝の1時間前までにはお風呂を済ませておくのがおすすめ◎
お風呂で一度上がった体温が、
ゆっくり下がっていくときに、自然と眠気が訪れると言われています🌙
⑥ 寝室に電子端末を持ち込まない

テレビやゲーム、スマホなどの電子機器が発する光(ブルーライト)は、
脳を活性化させてしまい、眠りの質が下がる原因にもなります。
眠る前は、できるだけ画面を見ない時間を作ったり、
寝室に端末を持ち込まないようにするのもおすすめです🌙
- 使用・充電はリビングだけにする
- 寝る前の使用時間を決めておく
など、家庭ごとのルールを決めておくと安心ですね。
また、目覚まし時計もスマホのアラームではなく、
子どもが“気に入った目覚まし”を選ぶことで、朝起きるのが楽しみに変わることも。
▼ 電子端末についてはこちらの記事もおすすめ。
- 🌿 小学生のタブレットルール 使用してわかった実体験と親がイライラしない仕組みづくり
⑦ 週末も平日と同じ時間に寝る
お休みの日こそ、つい「ちょっと夜ふかし…」「朝もゆっくり…」したくなりますよね。
でも、週末の起きる時間がズレることで、夜の入眠リズムが崩れ、
“平日の朝がつらくなる”悪循環につながることも。
せっかく整ってきた生活リズムが崩れてしまうと、
子どももまた1週間かけて戻す…という負担に。
できるだけ、週末も平日と近い時間での「就寝・起床」を意識すると、
朝の目覚めがスムーズになりますよ。
実際に我が家のルーティーンを少し紹介♪
21時には電子機器、強制終了のお知らせ。
そこからは就寝準備モードに入って、親子で布団へ。
娘はお気に入りの本を少し読んでから、消灯。
親の私も一緒に布団に入って、全員で“おやすみモード”に突入します🌙
翌朝6時には自然と起きて、
YouTubeやあつ森など「朝のお楽しみ時間」を満喫してから1日がスタート。
📌 朝の流れはこんな感じ:
- 6:00 起床 → YouTube&あつ森でゆったり時間
- 7:00 朝食&学校準備
- 7:55 「いってきまーす♪」
無理せず、“続けられるリズム”を一緒に作っていくのが我が家のスタイルです。
それでもダメな朝は…?ママの“困った”への対処ヒント
無理やり起こすのは逆効果なことも

中々起きてこない子どもにイライラして、
つい「いつまで寝てるの!」って怒っちゃうこと…ありますよね。
うちの母がまさにそう、1階から大声で叫んで起こすタイプでした(笑)
朝って、1日のスタートだからこそ
怒らず・あたたかく起こされると、子どもも気分よく動ける◎
気持ちよく起きられるような工夫って、
実は親子関係にもじんわり効いてくるな〜って思います🌼
普段から中々起きられない子には、少し早めに声かけをしてあげると
ママも余裕をもって接することができますよ。
💬 私は、母の“叫んで起こすスタイル”とは真逆の起こし方。 「娘ちゃん♡6時ですよ〜」 「寝顔かわいい‼ほっぺた食べちゃう‼」 ぎゅっと抱きしめると、さすがに娘も目が覚めて… 母としては朝から最高の癒しタイムです🥹 …そのうち逆に怒られるようになるのかな(笑)
体調や心のサインかも?じっくり見守ってみて◎
「夜ちゃんと寝たのに起きられない」「毎朝グズグズしている」
そんなときは、ちょっとした“サイン”を見落としているだけかもしれません。
- 午前中だけ元気がない、ぼーっとしてる → 自律神経の乱れかも?
- 起きられない+学校に行きたがらない → 学校でなにかあるかも?
- 夜ぐっすり眠れていない → 鼻づまり、アデノイド、寝苦しさの可能性も◎
“いつもとちがう”が続いたら、まずは見守ってみてくださいね。
💡心配なときは、病院や学校など、頼れる場所に相談するのもひとつの手です🌷
朝日を浴びて、朝ごはんを食べよう

曇りや雨の日って、なんだかずっと眠かったり、ぼーっとしたりしませんか?
それは、朝日を浴びることで整う「体内時計」がリセットされていないからかもしれません。
朝起きたらまずカーテンを開けて、自然光をあびることで
“朝のスイッチ”がしっかり入るようになります🌞
さらに、朝ごはんでエネルギーを補給することで脳がシャキッ!
一日をスムーズに始めることができます◎
たとえ寝起きが悪い日でも、余裕をもって起きて、ゆっくり準備するだけでもOK✨
からだと心が、少しずつ朝モードに切り替わってくれますよ。
まとめ|生活リズムはすぐには変わらない。だからこそ、ゆっくり・じっくり向き合って◎
「よし、早く寝かせたぞ!」と思っても、
翌朝からスパッと早起きできる…なんてことは、なかなかありませんよね。
生活リズムを整えるのって、一日二日で劇的に変わるものではなくて、少しずつ整えていくもの。
しかも子どもによっても個人差があって、
“この子に合ったやり方”を見つけるまでには時間がかかることも。
だからこそ焦らず、まずは
「夜、少し早めに布団に入ること」から始めてみてくださいね。
ママも子どもも、無理せず少しずつ。
一緒に“気持ちよく朝を迎えられる”日を増やしていけたら、それで十分です🌼
🔗 あわせて読みたい
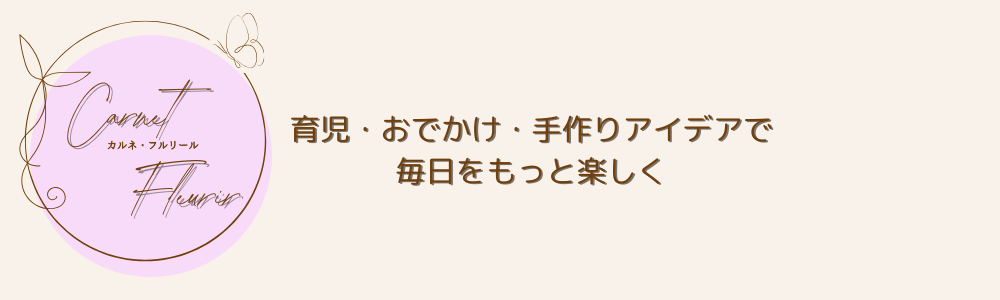
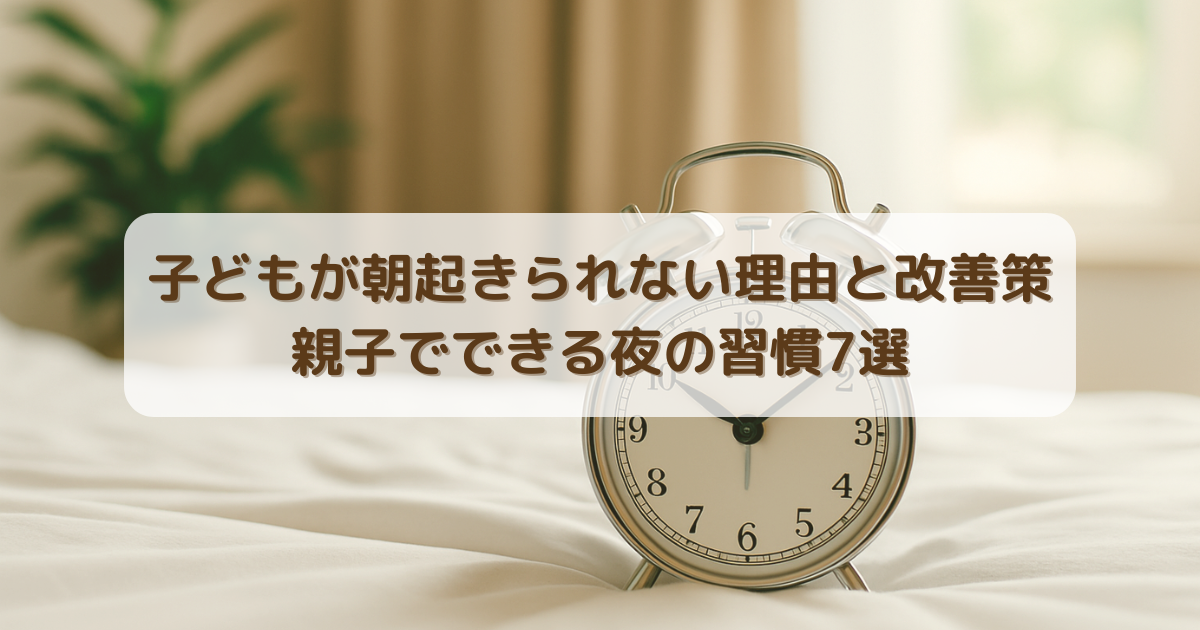


コメント